通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対する特別支援教育に関する問題です。
過去問で問われたことのある内容ばかりでしたね。
問123 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対する特別支援教育について、最も適切なものを1つ選べ。
① 通級による指導の対象となる障害には、肢体不自由は含まれない。
② 特別支援教育に関する校内委員会は、校内の教員以外は加わることができない。
③ 通級による指導を受ける児童生徒に対しては、個別の教育支援計画の作成が義務付けられている。
④ 校内支援体制の整備は、学校を管轄する教育委員会がリーダーシップを発揮して行うことが求められている。
選択肢の解説
① 通級による指導の対象となる障害には、肢体不自由は含まれない。
③ 通級による指導を受ける児童生徒に対しては、個別の教育支援計画の作成が義務付けられている。
「通級による指導」の制度上の位置づけとして、学校教育法第81条第1項においては、幼・小・中・高等学校において障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うことを定めており、すべての学校において特別支援教育が実施されることとされています。
その上で、通級による指導は、学校教育法施行規則第140条及び第141条に基づき行われています。
第140条 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項(第79条の6第1項において準用する場合を含む)、第51条、第52条(第79条の6第1項において準用する場合を含む)、第52条の3、第72条(第79条の6第2項及び第108 条第1項において準用する場合を含む)、第73条、第74 条(第79条の6 第2項及び第108 条第1 項において準用する場合を含む)、第74条の3、第76条、第79条の5(第79条の12において準用する場合を含む)、第83条及び第84条(第108条第2項において準用する場合を含む)並びに第107条(第117条において準用する場合を含む)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
一 言語障害者
二 自閉症者
三 情緒障害者
四 弱視者
五 難聴者
六 学習障害者
七 注意欠陥多動性障害者
八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
上記の通り、通級による指導は、障害に応じた特別の指導を通常の教育課程に加え、又はその一部に替えて行うものであり、通級による指導を受ける児童生徒については、特別の教育課程を編成する必要があります。
上記の140条で「…の規定にかかわらず」とされている学校教育法施行規則の各条文には、小・中・高等学校の教育課程を編成する教科等や授業時数、教育課程の基準が各学習指導要領に基づくことが定められています。
通級による指導のために特別の教育課程を編成するには、これらの規定の適用を外しておく必要があることから、このように規定されているわけです。
また、第八号で定められている「その他」に該当する障害は、肢体不自由、病弱及び身体虚弱であることが、「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」(平成25 年10月4日付け25文科初第756号初等中等教育局長通知)において明らかにされています。
なお、知的障害者については、知的障害者に対する学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な指導は、生活に結びつく実際的・具体的な内容を継続して指導することが必要であることから、一定の時間のみ取り出して行うことにはなじまないことを踏まえ、現在、通級による指導の対象とはなっていません。
ですから、選択肢①の内容については不適切であり、実際に通級による指導の対象となっていないのは「肢体不自由」ではなく「知的障害」であると言えます。
文部科学省によると、「個別の教育支援計画」は、障害のある児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的に作成されるものです。
また、この教育的支援は、教育のみならず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組が必要であり、関係機関、関係部局の密接な連携協力を確保することが不可欠とされており、他分野で同様の視点から個別の支援計画が作成される場合は、教育的支援を行うに当たり同計画を活用することを含め教育と他分野との一体となった対応が確保されることが重要とされています。
早期からの一貫した支援のためには、障害のある児童生徒等の成長記録や指導内容等に関する情報について、本人・保護者の了解を得た上で、その扱いに留意しつつ、必要に応じて関係機関が共有し活用していくことが求められます。教育委員会においては、幼稚園・保育所・認定こども園や障害児相談支援事業所等で作成されている個別の支援計画等を有効に活用しつつ、障害のある幼児に関する情報を一元化し、小学校へ引き継ぐなどの取組を進めていくことが適当です。
通級による指導の対象となる児童生徒の個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成や進学先等への引継ぎを促進するための体制を構築することが重要です(H25.10.4 通知、H28.12.9 通知参照)。
そもそも「通級による指導」の担当教師は、当該学校の教員免許状を有する者である必要があり、加えて、特別支援教育に関する知識を有し、障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的とする指導に専門性や経験を有する教師であることが必要ですが、特定の教科の免許状を保有している必要はありません。
ただし、各教科の内容を取り扱いながら障害に応じた特別の指導を行う場合には、当該教科の免許状を有する教師も参画して、個別の指導計画の作成や指導を行うことが望ましいとされています(H5.1.28 通知、H18.3.31 通知、H25.10.4 通知、H28.12.9 通知参照)。
高等学校における通級による指導の単位認定の在り方については、生徒が高等学校の定める個別の指導計画に従って通級による指導を履修し、その成果が個別に設定された目標からみて満足できると認められる場合には、当該高等学校の単位を修得したことを認定しなければならないものとされています(H28.12.9 通知参照)。
このように「通級による指導」であっても個別の指導計画を作成することが定められています。
以上より、選択肢①は不適切と判断でき、選択肢③が適切と判断できます。
② 特別支援教育に関する校内委員会は、校内の教員以外は加わることができない。
④ 校内支援体制の整備は、学校を管轄する教育委員会がリーダーシップを発揮して行うことが求められている。
小・中学校における特別支援教育の全校的な支援体制を確立するに当たって、校長自身がこのことの意義を正確にとらえ、リーダーシップを発揮することが大切です。
そのためには、各教育委員会等が実施する研修に参加したり、校長会等での情報交換を活発に行ったりすることによって、常に認識を新たにしていく必要があります。
学校における特別支援教育の推進は、校長の指導性の発揮いかんによって大きく変わるものです。
校内体制については、校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名、学校内外の人材活用、近隣の盲・聾・養護学校や関係機関との連携等、さまざまな角度からの推進が求められます。
また、校内支援体制の構築、校内委員会による児童生徒の実態把握、個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成、支援の実施、評価、改善のプロセスについて、校内全体で取り組めるよう校長がリーダーシップを発揮していくことが大切です。
校内における全体的な支援体制を整備するために設置されるのが校内委員会になります。
校内委員会の役割としては、以下が挙げられます。
- 学習面や行動面で特別な教育的支援が必要な児童生徒に早期に気付く。
- 特別な教育的支援が必要な児童生徒の実態把握を行い、学級担任の指導への支援方策を具体化する。
- 保護者や関係機関と連携して、特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する個別の教育支援計画を作成する。
- 校内関係者と連携して、特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する個別の指導計画を作成する。
- 特別な教育的支援が必要な児童生徒への指導とその保護者との連携について、全教職員の共通理解を図る。また,そのための校内研修を推進する。
- 専門家チームに判断を求めるかどうかを検討する。なお、LD、ADHD、高機能自閉症の判断を教員が行うものではないことに十分注意すること。
- 保護者相談の窓口となるとともに、理解推進の中心となる。
※これらの機能を一度にすべて満足させなくとも、徐々に機能を拡充していく方法をとることでこれらの基本的な役割を満たしていくことも考えられます。
支援までの手順としては、校内における支援を開始するまでには、保護者の理解のもとに、必要に応じて外部の専門家による判断等を踏まえて、実態把握と必要な支援内容を明確にし、校内委員会による教職員の共通理解を図りながら進めていくことが大切です。
実際の支援に至るまでの手順は、児童生徒によっても、また、学校の支援体制によっても違いがありますが、一般的には次のような手順が考えられます。
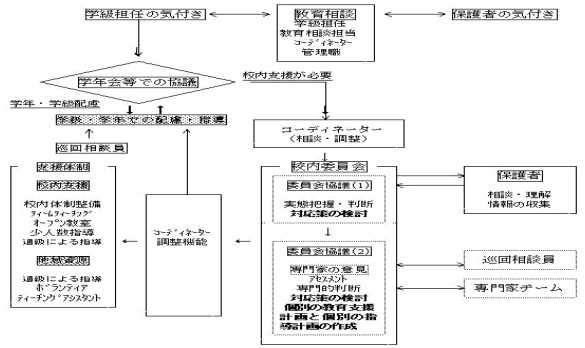
構成員ですが、各学校の規模や実情によって一律には考えられませんが、例えば、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、通級指導教室担当教員、特殊学級担任、養護教諭、対象の児童生徒の学級担任、学年主任等、その他必要に応じて外部の関係者が考えられます。
上記からも明らかなように、校内支援委員会は好調がリーダーシップを発揮して行うことが求められています。
また、校内支援委員会では、外部の専門家から助言や判断をもらうこともありますから、当然、支援委員会に入ることになります。
よって、選択肢②および選択肢④は不適切と判断できます。